【日 程】令和3年10月15日
【山 名】大山
【標 高】1,252m
【天 候】曇り
【メンバー 】福福
【タイム】
ケーブル下バス停9:30--9:42男坂登り口9:50--10:36阿夫利神社下社10:40--12:06大山13:05--14:07見晴台14:13--14:38阿夫利神社下社14:39--15:05大山寺15:14--15:27ケーブル駅15:27--15:38ケーブル下バス停
古来より大山は農民にとっては雨乞の、漁民にとっては豊漁祈願の山だったが、江戸時代に現世利益を願う庶民たちの信仰の対象になり、江戸から2,3日で行かれる手軽な行楽地として「大山詣り」が隆盛を極めたという。
現在においても人気の山ではあるが、山登りという構えた形ではなく、気軽な行楽地として認識されているように思える。大山詣りの伝統が今でも引き継がれているからだろうか。この日は晴天を期待していたのだが、車窓から見る大山は中腹より上は雲の中に隠れてちょっとがっかりだ。
小田急線の伊勢原駅で降りると北口駅前に阿夫利神社の大鳥居がある。現在は山麓までバスで行ってしまうが、昔の大山講の人達はこの鳥居をくぐって元気に歩いて行ったのだろうなぁと江戸時代の様子を想像してしまった。ところが家に帰ってから調べてみると、鉄道が通るようになってここからスタートする人が増えたので昭和になってから小田急電鉄が新たに設けた鳥居だと分かった。ありもしない光景を想像したのは私の早とちりだった。ちなみにこの鳥居を一の鳥居とすることが多いが、一の鳥居は藤沢市の四ツ谷分岐にあり、二の鳥居、三の鳥居も別の場所にあるそうである。
満員のバスを終点のケーブル下で降りると、階段に沿って並ぶ土産物店等の店並みを通り抜けていく。平日の早い時間帯なのでまだ営業している店は少ないが、以前来た時に豆腐料理を食べたのはこの店だったとか、懐かしく思い出しながら階段を登っていく。
土産物店街が終わった所にケーブルカーの乗り場があり、そこを過ぎると道は男坂と女坂の二手に分かれる。右手の男坂方面に進むと見上げるような石段があったので、ストックを出してこれからの登りに備えた。石段登りは一つ終えると、また次が現れるという繰り返しでかなりハード。ヨレヨレしながら登るうちに賑やかな声が聞こえてきて、園児達が保育士さん達に付き添われて登っているのに追いついた。こんな小さな子供達にこのルートを登らせるとは体力と根性の鍛錬を目的とした体育会系保育園なのか。
膝や腿の筋肉に負担を感じながらようやく阿夫利神社下社に到着して、山行の無事を祈ってから正面左手の登拝門を潜り大山山頂を目指す。大山登山は下社までケーブルカーで上ってそこからスタートというのが一般的で、男坂や女坂は一応参道歩きの範疇になる。とは言え参道歩きのほうが頂上までの道よりもキツイのだが。、
大山は常緑樹が多くおまけにガスっているので雰囲気が暗い。加えて湿った土が滑りやすく快適な登りとは程遠いのだが、こんな天気でも行き交う人は多く、それも若い人達が多い。皆、頂上からの展望を期待してただろうにお互い残念なことだ。
あせらずゆっくり上って丁度お昼頃に山頂に到着した。奥の院は閉まっていたが、山頂周辺のベンチなどで大勢が休んでいる。時にガスが切れて青空が覗くこともあったが、それは頭の上だけのことで、すぐにまたガスの壁に囲まれてしまう。
我々は山頂標識のすぐ横で昼食をとってから、下りは見晴台経由のコースにした。このコースには石段はない代わりに木製の階段や木道がやや過剰気味に整備されていてやはり歩きにくい。ただ、落葉樹の多い箇所もあって林が明るいのでその点は良い。南からの冷たい風に逆らって下っていくとベンチと東屋が整備された見晴台に着いた。雲の下に出たので厚木方面の市街地の一部が見下ろせるものの、展望はこれだけで振り返っても大山はまだ雲の中だった。ベンチで一休みしてから山腹に付けられた下社への道を進むと、巻道なのでこれまでのような階段はなく気楽に歩ける。
途中、大杉と二重の滝の見所を過ぎて下社に戻り下りは女坂経由にした。女坂と言ってもやっぱり急な石段があるのだが、このコースの良い点は大山寺を通ることで、ケーブルで往復してはこの寺には寄れない。丁度ご開帳の日だったからか祈祷の声が殷々と山中に響いていた。土産物店街に戻り朝と同じ通り抜けの道をバス停に下ったが、開いている店が意外と少ないのはやはりコロナの影響なんだろうか。
コロナと言えば今回は山ですれ違う人が多かったので、口鼻を覆う為に首に巻いた手ぬぐいを上げたり下げたりが忙しかった。会った人達の4分の1位はマスクを付けたまま登り下りしている様子で皆さん苦労している。早くこういう不自由な山歩きからは開放されたいものだが、それも阿夫利神社の神様にお願いしてくれば良かったか。
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→
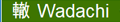
次の山行報告へ
| 







