【日 程】令和3年10月10日
【山 名】三頭山(西峰)
【標 高】1,527m
【天 候】曇り時々小雨
【メンバー 】福福
【タイム】
鶴峠9:32--11:08神楽入ノ峰11:08--11:45三頭山(西峰)11:49--12:03避難小屋12:52--13:11三頭大滝分岐13:11--13:55三頭大滝13:59--14:23都民の森バス停
山歩きに出かける日は感染予防の観点から人の少ない平日を原則にしている。とは言え所要との兼ね合いでそうも行かない時があり、今回は久々に日曜日の山行となった。混雑は覚悟するしかないが、反面土、休日は交通の便が良くなることもあって、平日には運行していない鶴峠の登山口へのバスが使えるという利点があった。
中央線上野原駅前のバス乗場に我々が到着した時には既に長蛇の列が出来ていて、その最後尾につくことになったが、幸い増発バスが用意されてほぼ1時間の乗車時間を立ちっぱなしという事態にはならなかった。、
終点の鶴峠のトイレのあるバス転回場でバスを降りると、準備の出来た者から三々五々出発していき、ここでもほぼ最後尾での出発だった。皆の後を付いていったら逆方向の奈良倉山に向かっていることが分かり、慌ててバス地点に戻ってから再スタートする。
登り始めはお決まりの植林帯だが、やがて山腹のトラバース道を行くようになると尾根の北西斜面に広葉樹の林が広がるようになる。ブナの木も多くスッキリ伸びた姿勢の良いブナが目につく。まだこの辺りでは紅葉は始まっていないが、急登のない歩きやすい道に気持ち良く足が前に出る。p1322を巻いた先で道が二手に分かれ、右が尾根ルートで左が引き続きの巻道ルートだ。尾根ルートには立木にテープが巻かれてはいるが分岐標識などはない。このまま巻道を行ったほうが楽しそうだが、この道は三頭山山頂から北に延びる尾根を150m程下った鶴峠分岐に出てしまう。頂上を直接目指すなら尾根コースを選ぶのが正解だ。その尾根コースを登ると植林との境界を行くようになり林の雰囲気はこれまでと異なり、当然ながら傾斜も増してくる。
ちなみに今回の登りで私は心拍数をモニターしながら登っているのだが、私の安静時の心拍数は58で、それが登りだすとまもなく100を超え、その後もジリジリと上がっていく。どこまで上がるのだろうと見ていると、最終的に116まていって以後これを越えることはなかった。この結果をカルボーネン法による計算式「目標心拍数=(220−年齢−安静時心拍数)×運動強度(かなりきつい70%・ややきつい60%)+安静時心拍数」に当てはめてみると、ややきついとかなりきついの間の数値(運動強度65%)であるようだ。知りたいのは心拍数と生理的な疲労度の関係なのだが、疲労度については数値化されていないのでよく分からない。ただこの心拍数で歩き続けるとかなり疲れる。
尾根道は神楽入ノ峰のプレートが掛かった小ピークを越えなおも登りが続く。お天気の方は登り始めが曇り空で時折薄日の差すこともあったが、やがてガスの中に入ってしまい小雨もパラつくという期待外れの天気になってしまった。
やがて人の声が聞こえるようになるとそこが三頭山山頂(西峰)の広場だった。三頭山には他に中央峰、東峰のピークがあるが、ここが最も山頂らしい場所なので憩う人達も常に多く、生憎の天候にも関わらずこの日も大勢の登山者が集っていた。
予定していた他のピークは省略して、雨を避けるため避難小屋を目指して国境稜線を南に下ると、ムシカリ峠を過ぎた先に建物が見えてきた。中に入ると十数名の登山者が休んでいたが、幸い窓際にスペースを確保できたので、ゆっくり昼食がとれた。
休憩後は引き続き尾根を南下し、三頭大滝への標識の所(ハチザス沢ノ頭)で主尾根を外れ左の枝尾根を下ると枝尾根を下りきった先に三頭大滝がある。流量はさほどでないが落差のある立派な滝で滝見学用の吊橋から滝全体が望める。滝から先は都民の森の遊歩道になり、ゆったり歩いて駐車場脇のバス停に計画通りの時間に到着した。ここも長蛇の列が出来ていたが、やはり増発バスが出たので席に座ることが出来て助かった。
バス終点の武蔵五日市駅からはホリデー快速という土・休日運行の列車にギリギリ間に合い締めくくりも申し分なかった。この列車は中央線直通と具合も良く山ヤさん専用列車の観があり、あちこちで下山祝のビールを開けている。ただ、一口飲むたびにマスクを上げたり下げたりしているのが今ならでは光景だった。最後のこの列車だけは立ちん坊になってしまったが、まぁ日曜日に出かければこんなものだろう。
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→
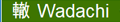
次の山行報告へ
| 







