【日 程】令和3年10月5日
【山 名】倉岳山、高畑山
【標 高】倉岳山990.0m、高畑山981.8m
【天 候】晴れ
【メンバー 】福福
【タイム】
梁川駅9:06--9:25倉岳山登山口9:34--10:52立野峠11:03--11:33倉岳山12:31--12:52穴路峠12:54--13:25高畑山13:37--14:28石仏14:28--14:59小篠14:59--15:29鳥沢駅
コロナの第5波に伴う緊急事態宣言が9月末で解除され、山登りが再開できることになった。いやぁ長かった。やっとという思いだ。他県への移動も可能となったことで、前から行きたかった山梨県の中央線沿線の山を計画してみた。
駅からそのまま歩き出すことが出来て、縦走コースが取れる倉岳山と高畑山を今回選んでみたのだが、どちらも大月市が選定した「秀麗富嶽十二景」の第9番目に選ばれている富士山の展望台というのが楽しみだ。
梁川駅で下車し桂川にかかる長い橋を渡る。橋の上から見下ろすとこの辺りの渓谷は随分と深い。この流れがこの先の相模湖に注いでいるわけだが、思いの外山深い印象を受ける。
橋を渡り終えると上り坂が続き道路脇の人家もまばらになる。やがて道路右側の石碑のあるところから山道が始まり、女性二人組がこれから登ろうと準備をしていた。我々の方は登山口は更に先ではないかと思い、そのまま道路を進んで大きく左にカーブするところまで行ってみたが登山口らしき所はなく、結局あの場所がそうだったかと納得して戻ってからのスタートとなった。ちなみに石碑と思ったのは登山口と書かれた標石だった。
登山道は終始沢沿いの道で何度も小沢を横切りながら標高を上げていく。気温は高めだが流石に10月の風は爽やかで、汗ばんだ体に心地よい。
水の流れが消え水音も完全に無くなるのが標高700m辺りで、そこから山腹に取付き小さな尾根を登るとほどなく立野峠に着く。桂川の南側に連なる秋山山系の主稜線に達したわけだが、人の往来の多い奥多摩の山に比べると、主稜線と言ってもいささか地味な印象を受ける。
峠での小休止の後、進路を西に変えて尾根道を小ピークをいくつか越えながら標高を上げていくと三角点とベンチのある倉岳山山頂に着いた。何はともあれ南側の景色を見てみると雲の上に富士山が浮かんでいた。光線の加減と高い気温のせいでスッキリというわけには行かないが、富士山の展望地であることは確認できた。
眺めを楽しんだ後は誰もいない山頂でベンチを占有して昼の支度を始める。コッヘルとフライパンを何十年ぶりかに新調したので、いつもならお湯を沸かすだけで済ますのを、ちょっと料理ぽいことをしてみる。ただ、料理の最中に鍋から吹きこぼれたお湯で右手親指を火傷してしまった。以前のコッヘルは沸騰すると蓋がカタカタ浮き上がって蒸気を逃してくれたのだが、新しいものは蓋がきついので前触れ無しで、いきなりお湯が噴き出して、柄を握っていた手にかかってしまったのだ。痛い思いをして新製品の特性を学んだと自分を納得させるほかなかった。
そんなことでたっぷり頂上での時間を取っておいたつもりが、出発が計画より遅れてしまい、これがの後々の慌ただしい行動の原因になった。
倉岳山山頂から120m程西に進んでから尾根を外れ、山腹の急勾配の道を下る。どんどん標高を下げて下りきった所が穴路峠で先程の立野峠同様に稜線を行く道と峠越えの路が十文字に交わる峠らしい雰囲気の場所だ。峠の標高が840m前後でこれから向かう高畑山は倉岳山とほぼ同じ高さなのでそれなりの登り返しになるが、峠から30分程で高畑山山頂に着いた。こちらも富士山の眺めはあるものの、さきほどより雲が増えてしまったのが残念だった。ちなみにこの山頂にはベンチや三角点はない。
高畑山から下山口の鳥沢駅までは結構長い。途中の穴路峠からの道との合流点に石仏が祀られているのを見つけた。峠越えの道が往時の生活路や交易路であった証であるが、今は登山者を見守ってくれているのだろう。山中は広葉樹の自然林で気持ち良く歩けたが、足の筋力の弱いかみさんは痛みを訴えて途中で止まったり、時には足がつってしまったりしていつもながら下りには苦労している。それでも列車の時間が迫っているため集落に入ってからは早足で歩き通し何とか列車到着の3分前に鳥沢駅に到着した。
そんなことで最近とみに慌ただしい山行の終え方が続いているようにも思えるが、次回はもう少しゆったりとした山歩きが出来るようにと思っている。
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→
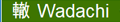
次の山行報告へ
| 







