【日 程】令和3年11月15日
【山 名】扇山、百蔵山
【標 高】扇山1,138m、百蔵山1,003.4m
【天 候】はれ
【メンバー 】ふく
【タイム】
鳥沢駅前バス停7:52--8:35山谷登山口8:48--10:00扇山10:15--10:52カンバノ頭10:52--11:55百蔵山12:39--13:15百蔵山登山口13:15--14:02猿橋駅
今日はカミさんは家で留守番。絶好の山日和なのに一人だけ残して出かけるのもちょっと申し訳ない気がする。平日の早朝の電車は空いていて乗り換えも順調だったが、最後のバスへの乗り換えでつまずいた。鳥沢駅で列車を降りてトイレを済ませてから教えてもらったバス停に向かったのだが、何とバスは出た後。事前に調べておいたバス時刻が違っていたのだ。乗車予定だった鳥沢駅前から山谷行きのバスは平日のみの運行で、1日2本のみという超が付くような希少路線。列車を降りて真っ直ぐバス停に向かっていたら間に合っていたのにと思うと余計に悔しい。しかし、今更どうしようなく歩くしか無いと腹を決める。
車の多い幹線道路沿いを東に10分ほど進んでから国道と別れ左に折れると行き交う車の量はぐっと減り、とりあえずホッとするが道路歩きの先はまだ長い。いくら急ぎ足で歩いた所でバスに追いつくはずもなく、この遅れは休憩時間の短縮で取り返せるかなぁと考えつつ、山谷集落の近くまで来てもう一度地図を見直した。計画では集落を抜けて更に道路歩きを30分近く続けた後、恋塚という所から入山するつもりだった。しかし、直接山谷から登るルートを使えば、途中の山谷分岐で当初計画のルートに合流できて、距離も三分の一程度は縮められる。つまり山谷コースは短縮ルートになることが分かり、こちらにルート変更することにした。
山谷登山口は標識が一本立つだけの地味な登山口だったが、ここからの富士の眺めは素晴らしかった。それを目に焼き付けるようにじっくり眺めてから暗い植林の中に入る。杉林の道はやがて沢沿いに登るようになるが道が不鮮明になってきた。少し戻って赤い旗の立つところから対岸に渡り、なおも不明瞭な道の後に標識の立つ正規の道に合流出来て一安心。経験的に道迷いとか道間違いとかは下山時に起きると思っていたのだが、それを登りにやってしまうとは、自分のルートファインディング能力に不安を覚える。
その後の道はしっかりしていて迷う所も無くなり、標高820m辺りで植林を抜け落葉広葉樹の明るい林になると木の間から富士山を望むことも出来た。葉を落としきる前の林は日を受けて暖かく、そんな中を歩いていると何とも言えない心地よさと幸せを感じる。ツツジ群生地の標識を過ぎなお登ると主稜線に到達した。そこが山谷分岐で当初計画のコースにここで合流したことになる。そこから標高差で200m弱のなだらかな尾根を登れば待望の扇山山頂だ。
計画より50分も早く到着したので、ひょっとしたら私が今日の一番乗りかとも期待したが既に5,6人の登山者が休んでいた。広々とした山頂部にはベンチも備えられていて、お目当ての富士山はちょうどその方向だけ高い木がなく、窓から眺めるような感じで富士山が正面に見える。気の済むまで富士を眺めてから頂上を後にし、次の百蔵山に向かって広い尾根を下っていくと直ぐに大久保のコルに着く。このコルを目指して梨の木平から登るのが扇山への最短ルートなので車利用でこのコースを登る人は多いようだ。コルの先にある大久保山から北西に延びる尾根を下り始めると、日陰のため急に周りの空気が冷たくなり慌ててパーカーを羽織った。
カンバノ頭(818p)でこの尾根を離れ、西に進路を変えると以後はアップダウンの道になり宮谷への道を分けるといよいよ百蔵山への登りになる。左手に見える扇山の山頂が徐々に低くなっていくのを励みに登り続けてようやく山頂部の一角にある分岐標識に到着した。三角点のある百蔵山山頂はそこから150m程先にあって、扇山山頂を少し小ぶりにしたような良く似た雰囲気の場所で、先客が二人のんびり休んでいた。
私もここで富士山を眺めながら昼食を含め45分ほど休息した後に下山を開始した。葛野方面への分岐標識位置から100m程標高を下げると富士山と麓の町並みを見下ろすテーブル付きの展望台があり、それを過ぎると桧の植林帯に入ってしまい、ただ下るだけという単調な道になる。標高610m地点に水場があるので夏なら有り難い給水ポイントになるだろう。立派な門構えの和田美術館(一般見学はできない)を過ぎると後は舗装された道路歩きで、途中の見所は岩殿山くらいか。
終着地の猿橋駅に2時頃に到着して、当初計画では4時頃としていたので、バスに乗り遅れたにも関わらず2時間早めたことになる。それだけ歩きやすいコースだったわけで、晩秋のうららかな日差しの中、良いハイキングが出来たと、この日の一日の行動を振り返った。
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→ 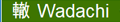
次の山行報告へ
|








