【日 程】令和3年11月6日
【山 名】牛奥ノ雁ヶ腹摺山、小金沢山、大菩薩嶺
【標 高】牛奥ノ雁ヶ腹摺山1,990m、小金沢山2,014.4m,大菩薩嶺2,056.9m
【天 候】晴れ時々くもり
【メンバー 】福福
【タイム】
すずらん昆虫館前バス停8:49--10:40牛奥ノ雁ヶ腹摺山10:47--11:20小金沢山11:53--12:57石丸峠12:58--13:26大菩薩峠13:30--14:08雷岩14:09--14:15大菩薩嶺14:16--14:21雷岩14:21--15:01福ちゃん荘15:03--15:18上日川峠
大菩薩連嶺とは北は鶏冠山に始まり大菩薩嶺を経て、南は滝子山に至る山並みを言うらしい。この内、私が歩いたことがあるのは大菩薩峠〜大菩薩嶺、黒岳〜牛奥ノ雁ヶ腹摺山それと滝子山だけで大菩薩連嶺の核心部分が抜けている。
そこで今回は牛奥ノ雁ヶ腹摺山から大菩薩嶺まで歩く計画を立ててみた。
ハイキングのメッカのような大菩薩へは、混雑する土、日は避けたい所だがバスが土、休日のみの運行なので何とも仕方がない。晩秋の11月初旬の土曜日、甲斐大和駅の改札を出るとバス停には既に長蛇の列が。ただ、バス会社も手慣れたもので次々と増発バスを出すので乗客が取りこぼされる事は多分無い筈だ、。それにしても小さな駅にこの賑わい。大菩薩への表玄関は塩山駅から甲斐大和駅に知らぬ間に移ってしまったようだ。
我々の乗車した2号車は約30分で登山口のすずらん昆虫館前に到着したが、乗客の大部分は終点の上日川峠まで行くらしく、降りたのは我々のみ。直後に到着した3号車から降りたのも一人だけと、ここから牛奥を目指す登山者は少ない。
バス停の所が登山口になっているので身支度を整えて歩き始めると紅葉した木々に朝日が射し込んで、晩秋らしい穏やかな雰囲気が何とも好ましい。林道に出て柔らかな日差しを浴びながらのんびり歩を進める内に林道終点に着き、再び山道が始まるが直ぐに舗装された道路に出る。道路を横断し標識を確認して登山道に入った筈が、踏み跡について登る内に獣害ネットに行き手を遮られてしまった。ネットの向こう側には登山道が見えているので、少し来た道を戻ってネットの隙間から正規の登山道に入ったが、一体どこで間違えたのだろう。
落葉広葉樹の明るい林に次第に針葉樹が混ざるようになるが、標高を上げても緩やかな尾根道は急登もなく歩きやすい。牛奥のピーク手前で笹原に立ち枯れの木が目立つ場所に来ると一瞬富士山が見えた。ほとんど雲に隠れていてカミさんのカメラはかろうじて姿を捉えていたものの、私の方は雲が写っていただけだった。
牛奥の山頂には数人の登山者が休んでいたが、前回我々が大峠から登ってこの山を目指した2012年11月には他の登山者の姿はなく、我々だけで赤ワインで乾杯したのを思い出した。肝心の富士山が見えないので長居することもなく次のピークである小金沢山を目出して出発する。この先は伸びやかな笹原が広がる、正にイメージ通りの穏やかな稜線で、時折日が陰って急激に気温が下がるのを除けば快適な尾根歩きだった。
ところが小金沢山での昼食後は道の様子が一変してコメツガ等の針葉樹の根っこや露岩が連なる細い稜線は歩き辛くこの通過に思わぬ時間を要した。狼平の笹原に出てホッとしたのだが、振り返ると小金沢山の東側は雲に覆われ全体の空模様も暗い。この日の天気は晴れたり曇ったりの繰り返しで、気温が低いのでパーカーを着たまま行動している。
天狗棚山へ登り返してから小広い石丸峠に下り次の熊沢岳を目指す。この山も暗い針葉樹に覆われていてどこがピークだか分からない内に通過して、下りにかかるとほどなく介山荘のある大菩薩峠だ。予想通りの混雑ぶりで、この先はコース上に人影を見ないということはなくなった。賽の河原から少し登り返した所に「標高2000m地点 2000年設置 塩山市」という標柱が有って、地図ではその後ろに碑のマークが入っているのだが、それがなんであるのか急いでいたので確認は出来なかった。
雷岩まで来てここから最高峰の大菩薩嶺までは数分の距離なのだが、下りに時間がかかるカミさんはここから下ると言うので、私のみ急ぎ足で頂上を往復した。魅力のある頂上ではないので行く必要があるかどうか迷ったが、一応縦走のけじめとして山頂写真を撮っただけで直ぐに引き返した。ガラ場の下りの途中でカミさんに追いつくと、程なく道はなだらかな道に変わる。道近くの林の中に子連れのメス鹿が何頭もいて盛んに笹の葉を食べていた。可愛いが鹿が増えるのもなぁと複雑な気持ちで見ていると、その気持ちが伝わるのか、私に向かって盛んに警戒音を発していた。
道はどんどん緩やかになって林を抜けると大勢が休む福ちゃん荘に到着した。これで予定のバスに間違いなく間に合う目処がたち、ここからは舗装路を歩いて終着地の上日川峠で待機していたバスに乗車出来た。ここでもバスは続々と増発されるようで、ほぼ満席になると予定時刻前でも出発していくので実に合理的だ。
と言うことで、土、日の混雑は嫌だが反面交通機関の便の良さもあり、利害相半ばというのが今回の感想である。、
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→ 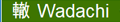
次の山行報告へ
|








