【日 程】令和3年10月30日
【山 名】滝子山
【標 高】1,620m
【天 候】晴れ
【メンバー 】福福
【タイム】
初狩駅7:57--9:29最終水場9:36--10:35檜平10:48--11:26滝子山三角点11:26--11:28滝子山12:30--13:28曲沢峠分岐13:28--14:10三丈の滝14:10--14:30道証地蔵14:32--15:21笹一酒造15:21--15:26笹子駅
滝子山には2010年にGo夫妻と一緒に登っているが、楽しかったという印象はあるものの、山の記憶は断片的で頂上の様子すら曖昧だ。そこで今回は再検証すべくカミさんと二人で出掛けてきた。コースは前回行った時と同じで次期もほぼ同時期だ。
初狩駅では10名程度の登山者が降りたが、殆どは高川山に向かうようで滝子山へは我々と単独男性のみだった。その単独男性は快足を飛ばして先に行ってしまったので、結局頂上までは我々二人のみの、人に会うこともない静かな山歩きになった。
駅前から国道20号線に出て、少し進んでから滝子山への道に入る。曲がり角にはちゃんと案内標識があり、この山も要所には標識が整備されているので分かりやすい。中央高速を潜って藤沢集落に入る手前に「この道を挨拶街道と呼び何人も必ず挨拶を交わすように」との告知板が有り、これには記憶があったのでもちろんきちんと言い付けを守った。
集落を抜けるとやがて沢沿いの山道になる。前回の報告に裾が汚れてしまったとあるのは多分この辺りのことで、そのためスパッツを用意してきたのだが、ぬかるみはそれほど酷くはなく、わざわざスパッツを付ける必要はなかった。
沢沿いの道から山腹の道に変わる所に最後の水場の標識が立っていて、矢印の指す方向に行ってみると貯水施設がありコックをひねると水が出るようだ。ただ、そこには「この水は手洗い用です」と書かれていた。山で水場と言えば常に水が流れている場所か湧き水のある所を想像するのが普通だ。水が必要ならすぐ下に流れている沢水を使えば良い話しでそこを水場とすべきだろう。ここに手洗水の貯水施設を作った人の考えが私には理解できない。
やがて稜線に出ると落葉広葉樹のトンネルを行くような気持ちの良い道になり、今日の上天気に合わせて気分も安らぐ。紅葉の方は色づいたものもあるが真っ盛りという感じではなくまだ少し早いというところか。
標高1,290mに檜平の標識があり、この辺りが小広くなっていて富士山を望むことが出来る。紅葉し始めた木々を通して青空をバックに白く雪をかぶったその姿は絵葉書のようだ。この日の最高の富士山はこの場所からのものだった。檜平から道は男坂と女坂の二手に分かれる。前回は男坂を登ったので今回は女坂経由で行こうとしばらく進んだのだが道形が判然とせず、結局引き返して男坂を登ることにした。
標高1,480m辺りからは平坦なプロムナード風の道になり、紅葉も鮮やかさを増してきた。中でもミネカエデの真っ赤なのが見事だった。少し傾斜の増した道を登りつめると二等三角点のある場所に出る。この地点(1,590.3m)を国土地理院では滝子山の標高としているが、頂上はこれより30m高く、山頂標識に書かれた1,620mが滝子山の標高とされている。
その頂上に着いて驚いた。ここまでの静かな山はどこへやら、狭い稜線状の山頂は人で溢れていた。天気予報からある程度の人出は覚悟していたがあまりの混雑ぶりだ。思うに初狩ルートはマイナーで多くの人は我々が下山路に予定している笹子からのルートか又は
寂悄尾根(南陵ルート)を利用しているようだ。何とか場所を確保して昼食の準備を始めたが、食事の終わる頃には富士山は雲に隠れてしまった。
檜平で富士山を堪能した我々は特に名残を惜しむこともなく、ごった返す山頂を後にして大谷ヶ丸方面に進むと白縫神社に出る。以前は木製の鳥居があったが朽ち果ててしまったらしく、今は小さな祠が残るのみだ。途中の分岐から大谷ヶ丸方面とは分かれ広々とした尾根道を下る。前回も感じたことだがこの辺りの林の雰囲気が牧歌的で実に良い。やがて道は人工林の目立つ沢沿いの道になり、面白みのない道をひたすら下るようになる。あまり滝っぽく見えない三丈の滝を過ぎて20分程歩くと道証地蔵の置かれた林道出合に出てこれで山道は終わるが、笹子駅まではまだ遠い。
次の列車に間に合うように急ぎ足で駅を目指すのは最近の我々のパターンで、今回もひたすら急ぐ。そして今はひっそりとしている笹一酒造の前を過ぎ笹子駅の長いホームを最後は走って何とか列車に間に合わせた。いや正しくは数十秒は過ぎていたのを列車が待っていてくれた。、
そんな事で十年ぶりの振り返り登山は、予定していた列車よりも早い時刻の列車に乗れて無事終了した。しかし、前回は笹一酒造で下山後の打ち上げを皆で楽しんだのだが、今回はもちろんそういうこともなく、考えてみるとコロナ禍での山登りはやっぱりわびしい。
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→ 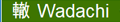
次の山行報告へ
|








