【日 程】令和3年12月14日
【山 名】小辺路
【標 高】果無峠1,060m
【天 候】晴れ
【メンバー 】福福
【タイム】
十津川温泉(蕨尾口)7:13--7:36果無峠登山口7:39--8:16果無集落入口8:16--9:27観音堂9:37--10:05果無峠10:15--12:33八木尾バス停12:33-12:54道の駅13:15--13:43三軒茶屋跡13:44--14:28熊野本宮大社14:45--15:03大日越え入口15:04--15:58--つぼ湯16:04--16:13湯の峰温泉宿
小辺路とは熊野古道のひとつで高野山から熊野本宮大社までのコースを言う。以前(2016年10月)に同じく小辺路の一部を歩いているので、その時の2回の報告とタイトルを揃えて(3)とした。
今回の出発点である十津川温泉へは近鉄大和八木駅前から新宮行きの路線バスに乗る。八木駅前発が11時38分、十津川温泉着が16時14分で、更に終点の新宮まで乗ると18時24分着となる。日本最長の路線バスというのはだてではないのだ。乗車時間の長いのはともかく、行けども行けどもというその山奥感に圧倒される思いだった。
久しぶりの泊まりの山旅を温泉で癒やした翌朝、宿を出ると思ったほど冷え込んでない。予報ではマイナス1度と言っていたが、5度以上はあるような気がする。お天気は快晴で暖かいとなれば良い山歩き日和になりそうである。
宿から国道を下って橋を渡った所で右手の道に入り、少し行くと果無峠登山口の石段が現れる。いよいよここから憧れの果無への道が始まると思うと気分も高揚する。
石段の後に石畳の道が続くいかにも古道という道を登る内にベンチの置かれた開けた場所に着く。川面や山の谷間に雲なのか朝霧なのか判然としないものが薄っすらと覆っている様子は絵画的だ。ここで少し薄着になってから更に登ると果無集落の入り口に着く。
NHK「新日本風土記」のタイトルバックに老夫婦の背中を撮している場面は多分この集落なんだろうと勝手に思っていたのだが、結局それらしき場所は見当たらずどうも私が誤解していたようだ。
集落を抜けると果無峠への登山口があり、傍らにバス停がある。ここに月曜日のみ一日2便運行の村営バスが上がってくるのだが、ちなみに今日は月曜日なので15分後にはバスが来るはずだ。峠を目指す登山者は我々の他にいるだろうか。
峠への道は坦々としていて足の運びも快調だ。天水田、山口茶屋跡を過ぎ標高830m辺りにお堂(果無観音堂)があり、お堂の前には休憩小屋、給水施設それにトイレまである立派な休憩場所だった。観音堂から道は傾斜を増してきていよいよ峠が近づいてきた感じがする。標高930mで麓の集落が見下ろせる箇所があった。このコースでは開けて景色を見ることができる所は殆どない。その代わりと言っては何だが、西国三十三観音と名付けられた三十三体の観音像が櫟砂古(いちざこ)から果無集落を経て峠を越えた先の八木尾へのルート上に配置されている(起点は八木尾)。旅人達は観音様のご利益にすがって辛い山越えを乗り切ったのだろう。
ようやく辿り着いた果無峠は今回のコース中の最高地点1,060mで、日の差し込む明るい峠だった。ちなみにそこに置かれていた観音像は十七番目のものだったので、尾根の両側に均等に割り振られているようだ。
峠から下っていくと標高630m辺りに前方が開けた箇所があり「本宮町を望む」との看板が立っていた。その直ぐ脇に三十丁石というのがあり、この上部にも二十丁石があったがいったいどこを起点としているのだろう。峠から2時間20分後に山道を終え、舗装道路をしばらく歩いて昼食を道の駅でとったが、このように山越えを含め集落を繋いで行くの古道の歩き方になる。昼食後は引き続き道路歩きの後に山中に入ると直ぐに三軒茶屋跡に出る。ここで中辺路と合流しシダの多い平坦路を進めば目的の熊野本宮大社だ。
お正月を迎える準備の進んだ大社でお礼参りの後、カミさんは今日の宿のある湯の峰温泉までバスで、私は歩いて向かうことにして、国道脇から大日越えのコースに入る。この道も石段で始まり石畳の道になる。まだ3時過ぎというのに日が傾いて山中は薄暗かったが、大日峠を超えると西日が入るようになり明るさが戻った。湯の峰王子を過ぎると直ぐにつぼ湯の横に出て今回の山旅はこれで終了だ。
この後、もちろんつぼ湯に入り傍らに掲げられた「小栗判官物語」を見て、小栗判官は四十九日の湯治の後に回復したが、30分以内一人400円也の薬効はいかほどであろうかと、お湯でふやけた頭で考えたのだった。、
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→ 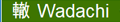
次の山行報告へ
|








