【日 程】令和3年12月9日
【山 名】陣場山、生藤山
【標 高】陣場山855m、生藤山990.3m
【天 候】晴れ
【メンバー 】ふく
【タイム】
和田バス停7:47--8:53陣場山8:55--9:13和田峠9:16--9:54醍醐丸9:55--10:55連行峰10:59--11:20生藤山11:22--11:26三国山12:00--12:12熊倉山12:12--12:59浅間峠14:00--14:52--上川乗バス停
中央線藤野駅からバスに乗れば15分とかからず終点の和田に着く。ここへは初めて来たのだが、バス停の隣にはトイレと休憩所のある登山者に優しい場所だった。そこで降りた登山者は私を含め男女合わせて4名、いずれも単独行で陣場山を目指すのは同じでもてんでに出発していく。カミさんの膝が本調子でないため私も今日は一人旅だ。
バスの進行方向に道路を少し歩いてから標識に従い右手に入ると直ぐに登山道ぽい道になる。雑木林の木々はまだ葉を残していて、紅葉の名残という風情だ。和田から陣場山へのコースは落合からのメインコースに比べるとスタート地点の標高が高いため頂上までの所要時間が短い言わば短縮コースになる。従って登るのも容易で1時間ちょっとで人影まばらな陣馬山山頂に着いてしまった。
陣場山と言えば富士山の眺めと白馬の像だが、お目当ての富士山は雲に隠れて見えず、やむなく白馬像をバックに自撮り写真を撮っただけで山頂を後にした。ここから北の和田峠に向かう道はまだ新しい木の階段が設置されていて、これが下まで続く。木の階段というのも風情がないし、歩き易くもないのだが、道の保護という面ではやむを得ないところがある。しかしここのはちょっとヤリ過ぎの感がする。
和田峠の茶屋はまだ閉まっていて人気がないので素通りして醍醐丸に向かって尾根を登り返す。この道は4月に通っているので、植林の中の展望もない退屈な道だということは知っている。途中の分岐からピークを経由しない巻道を選ぶ人が多いようだが、前回と同じコースで醍醐丸ピークに立ち寄ってみた。山頂の南側は植林、北側が自然林という尾根を境に異なる植生という良くあるパターンで、木製のベンチが三脚も置かれているが、眺めを楽しむと言うよりは単なる休憩用という意味合いなのだろう。前回は市道山から眺めを期待して登ってきたのに、ここに着いてがっかりした覚えがある。
醍醐丸から尾根を西に進み山の神の鞍部まで標高を下げてから連行峰に向けて200m程登り返しになる。連行峰は今回通ったピークの中では最も標高の高いピーク(1,016m)なのでここが一番の登りになる。登り着いた連行峰はピーク然としてなくて尾根道の途中という感じなのだが、それでも昨年12月以来1年ぶりという事で懐かしい。その時はここから木の間越しに富士山を見たのだが、今回は曇り空で富士山は無理だった。
連行峰から先はもう長い登りはなくなり、小さなコブを越えていくだけの快適な尾根歩きになる。その小さなコブさえも地図にはない巻道が用意されているし、尾根の両側はほぼ自然林という、これで富士山が見られれば言うことなしという尾根道だ。茅丸は脇を巻いて、次の生籐山手前にも巻道分岐があるが、これも巻いてしまうと頂上に寄れないので、ここは直登する。登り着いた生籐山山頂には女性6人パーティがベンチで休んでいて、私が頂上写真を撮っていると、どこから来たのかと尋ねられた。陣馬山を出発してから初めて出会った登山者なので、ゆっくり話もしたいところだったが、コロナ禍とあって手短に要件のみで切り上げた。
昼食は三国峠(山)でとる事にして生籐山を下るとものの5分で到着する。三国峠(山)は生藤山山頂より広く、テーブル付きのベンチもあって食事をするには具合がいい。そこでの昼食が終わった頃に反対側から今度は男性3人組がやってきたので挨拶を交わした。この季節の平日であってもやっぱり登る人はいるものだ。彼らに別れを告げて次の熊倉山に向かうとその途中に軍刀利神社元社というのがある。麓の軍刀利神社奥の院に当たるのだと思うが、この場所は小広くなっていて感じの良い場所だ。桜も植えられているので春なら花見宴会も出来そうだが、御神域ではやっぱり無理か。
元社から気持ちの良い尾根道を10分少々で熊倉山山頂に着く。これまでのピークと良く似た感じで特徴的なものはないので、そのまま通過して稜線上の最終地点である浅間峠を目指す。熊倉山からわずか40分ほどの距離なのに意外と遠く感じて、懐かしい峠の東屋が見えた時にはホッとした。
ただ問題はその到着時間が中途半端なことで一本前のバスには間に合わず、予定のバスまではバス停までの所要時間を差し引いても1時間20分の余裕がある。この時間を有効活用して次にピークを目指すには時間が足らない。結局東屋で焼酎の湯割りとチョコレートをかじりながら時間を潰したが、あまりセコセコ歩くと無駄な時間が生じることがあると少し反省したのだった。、
トップページへ戻る
ポイント写真及び山の位置はこちら→ 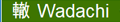
次の山行報告へ
|








